それは・・
森保一ジャパンじゃ、誰が出ても、基本的なチーム戦術イメージが、とても高いレベルで共有されている・・っちゅうこと。
それは、ホントに素晴らしいし、ストロングハンド森保一の面目躍如っちゅうことなんだ。
何せ・・
そう、世界中に散らばっている(微妙に異なるチーム戦術でプレーする!)選手たちが、一堂に会してから数日後には、このような素晴らしいサッカーを魅せつけちゃうんだから。
・・攻守ハードワークとリスクチャレンジマインドを絶対ベースにブチかます、ダイレクトパスを織り交ぜた素晴らしい組織コンビネーション・・
・・人とボールが、スムーズに、スピーディーに、そして正確に「動き」つづける・・
・・そんなチーム戦術的なベースが機能しているからこそ、スペースを効果的に攻略できる・・
・・だからこそ、個の勝負プロセスも最大限に活かせる・・
・・スピードを活かしたウラ取りコンビネーションあり、破壊的なドリブル突破あり・・
・・そして今日は・・
・・そう、浮き球やグラウンダーの必殺クロスを、ヘディングや足でブッ叩きつづけた・・
・・私は、たしかに6ゴール「しか」奪えなかったけれど、そこには、WM予選を戦うからこそ価値のある、進化したコンテンツが詰め込まれていたと、感じていた・・
ところで、モンゴルとの「実力差のバックボーン」というテーマ。
それを深掘りするのも、興味深い。
もちろん、フィジカルや基本テクニックじゃ、「以前」ほど大きな差はない(昔は、それぞれの国の実力差は、とても大きかったんだよ)。
また、心理・精神面(闘う意志)というファクターじゃ、モンゴルは、優るとも劣らない。
それじゃ、日本とモンゴル間の「あの差」を生み出していた、もっとも大きな要素は??
多分それは、「戦術イメージ」というファクターに集約されるんだろうね。
守備では・・
たとえば、相手の次のパスや仕掛けプロセスを「読む」チカラ。
日本選手たちのレベルは、とても高いから、モンゴルの仕掛けプロセスを予測し、先回りして効率的にボールを奪い返してしまう。
また、攻め込まれて局面デュエルに入ったとしても、その内実の差も大きい。
そう、前述した、フィジカルやテクニックの「微妙な差」が、ここでは、より大きなグラウンド上の「差」となって、より明確に表面化するっちゅうことだね。
とはいっても・・
スペース攻略という視点でアナライズする「攻撃」については・・
前述したように、ボールのないところでの人の動きの量と質に大きな差があることで・・
組織コンビネーションの内実で、決定的な差になってくるっちゅうわけだ。
そう、ボールを、美しく動かせるからこその、足許パスとスペースパスの効果的なコラボレーション(!?)
でも、今日のゲームでは・・
そう、ほとんどのゴールは、クロス攻撃からだったんだよ。
それは、とても興味深いグラウンド上の現象だった。
要は・・
「ワンツースリー・・」なんていう高度なコンビネーションを駆使した中央突破でも、クロス攻撃でも、ゴール機会を創りだせるということ。
そう、彼らは、どんどんと、最終勝負に「実効ある変化」までも生み出せるようになっているんだ。
もちろん、ミドル弾だって、サイドからの「アーリークロス&こぼれ球ヒット」だって、できる。
だからこそ、相手ディフェンスも、的確に、抑えのターゲットを絞り込めなくなる。
W杯予選じゃ、相手に中央ゾーンを固められて攻めあぐむ・・ってなゲームで、ヤキモキさせられたゲームは多かった。
それが・・
そう、あれほどの「仕掛けの変化」を効果的にブチかませるようになっているコトは、とても実利のある「進化&深化」って言えるんだよ。
ということで、何か、まとまりがないけれど・・
言いたいことのまとめ・・
・・森保一ジャパンは、集まれば、すぐにでも、共通の「チーム戦術ピクチャー」を描きながら、高度な組織サッカーを、高い実効レベルで表現できるまでに成長している・・
・・そして「それ」を基盤にスペースを攻略し、そこから繰り出す「個の勝負プレー」も、これまた、とても高い実効レベルでブチかませるようになっている・・
・・そして、これが特筆だったわけだけれど・・
・・彼らは、その最終勝負プロセスに、前述したように、様々な「変化」を加味できるまで進化しているんだ・・
とにかく、プロコーチ森保一さんは、関塚隆技術委員長と田嶋幸三会長の(そして彼らを支える優秀な技術スタッフたちの!)サポートに支えられ、とても、とても優れた仕事をパフォームしつづけてくれている。
同業者として、心からレスペクトするとともに、日本のサッカー人として、心からの感謝も表する筆者なのであ〜る。
ガンバレ〜ッ!!・・森保一〜〜っ!!!
あっと・・
最後に、選手個々についても、簡単に・・
まず、遠藤航。
久しぶりの先発だったこともあって(!?)、最初の頃は、とても注意深く、セキュアな(安全・安定志向の!?)プレーに終始していた。
でも、時間の経過とともに、ボール奪取(守備プロセス)だけじゃなく、攻撃でも、どんどんペース
アップしていったよね。
目立たないけれど、彼がブチかましたチェイス&チェックによって、(それをベースに!)何度日本が、次のチャンス構築プロセスを効果的に演出できたことか。
そして最後は、鎌田大地のヘディングゴールにつながった「低く抑えたミドル弾」に、彼のパフォーマンスアップの内実が集約されていたように感じた。
もちろん、絶対ゲームメイカーである柴崎岳の「パートナー・ライバル」である橋本拳人も、素晴らしいプレーをつづけているわけで、この二人の切磋琢磨にも期待が高まる。
長友佑都。
カタールWMを、35歳で迎えることになるのか!?
でも、彼の、日々のストイックな精進を考えれば(もちろん報道ベースの知識にしか過ぎないけれど・・ネ)、そんな心配なんて、吹っ飛んじゃうよね。
年齢的な(高みで安定したパフォーマンスという!)視点じゃ、吉田麻也にも、まったく不安はない。
右サイドバック・・
もちろん酒井宏樹がファーストチョイスだろうけれど、そこには、安西幸輝っちゅう、実のあるコンテンダーも出現している。
コンテンダーといえば、前線カルテットのライバル争いからも、目が離せないよね。
今回は、大迫勇也がいなかったわけだけれど、そのカルテット候補は、中島翔哉、南野拓実、伊東純也、永井謙佑、そして今日は出番がなかった、言わずと知れた堂安律と久保建英。
また、浅野拓磨や鎌田大地もいる。
とにかく、期待が高まりつづけるじゃありませんか・・へへっ・・
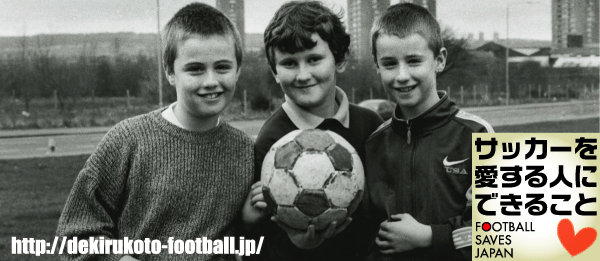 ”Football saves Japan”の宣言に賛同します(写真は、宇都宮徹壱さんの作品です)。
”Football saves Japan”の宣言に賛同します(写真は、宇都宮徹壱さんの作品です)。