ロシアとウルグアイの試合を観ながら、そんなコトを考えはじめていた。
要は、ウルグアイの方が、明らかに「強い」のだけれど、そんな全体的なチカラの差は、どこから生まれてくるのか・・っちゅうテーマ。
現象的には、もちろん、ウルグアイがゲームの流れを支配している(ボールをより多くキープし、攻守にわたって効果的なプレーができている!?)ってな感じなんだろうけれど・・
差のバックボーンなんて、分かり切っているだろ・・ってな声が聞こえてきそうだけれど・・
でも、チカラの差の背景ファクターには、様々なサッカー要素が複雑に絡んでいるから、それをシンプルに表現するのは、以外と難しいんだよ。
でも・・
そう、トライはしてみよう。
フィジカル、技術、戦術、心理・精神要素、そしてツキなどといった、サッカーにおける最重要ファクターをベースに、こんな感じのアーギュメント議論はいかが??
まず、フィジカル。それについては、大きな差はないでしょ。
ではテクニック。
それは、詳細にアナライズする価値はありそうだね。
そう、トラップとキックという根源テクニックで、少しずつ、「差」が感じられるんだ。
もちろん、どのようにボールをトラップするのかは、戦術的なイメージも複雑に絡んでくるから、足許にしっかりと止められるとか、そんなにシンプルに表現できるシロモノじゃない。
それに、トラップには、「次のデュエル」や「次の展開」等などの、周りとのアクション要素も加わってくるよね。
やっぱり、技術と戦術は、つねに一体なんだよね。
そう、一つのトラップは、次の攻撃の起点イメージ、味方とのコンビネーションイメージ、逆に、相手とのデュエルイメージ等など、ホントに多くの要素が絡み合った結果としてのグラウンドの現象っちゅうわけだ。
だからこそ、場数(経験の積み重ね)が大事だし、それがあって初めて、それらの要素をアタマのなかでプロセスし、最良のボールの止め方が一瞬でイメージできるっちゅうわけさ。
ちょっとディスカッションが錯綜しちゃいそう。
だから・・単純にまとめよう・・
要は、トラップからキック(パスやクロス、シュート等など)までの一連アクション、また逆に、相手との局面デュエル等などの「内実」を進化させるために、様々なスキルと戦術イメージが、有機的にシンクロしていなきゃいけないっちゅうことだ。
ありゃ〜・・もっと分かり難くなってしまった。
フ〜〜ッ・・
もちろん、そんな「個のファクター」以外にも、ボールの奪い方(協力プレスや追い込み等など)とか、攻撃では、スペースを効果的に活用できるためのボールがないところでの動きの量と質などといったグループ戦術的ファクターを洗練させることも大事になってくる。
まあ、チカラの差は、サッカー要素のすべてに関わって生まれてくるっちゅうことか・・。
フ〜〜ッ・・
何か、うまく表現できないね。
まあ、とにかく、攻守にわたる個人のテクニックが、すべてのスタートラインというのは確かな事実だから・・。
そうそう・・
内容と結果の一致という視点で、ドイツが本当の復活を遂げたミレニアム以降、「まずテクニックを磨くところから再生する・・」ということで、ドイツ全土に大号令が飛んだんだよ。
わたしは、その号令を出した人たちを個人的に知っているし、何度かは、その大事なミーティングに同席させてもらったこともあった。
そりゃ、ものすごくエキサイティングな経験だったよね。
そこでは・・
戦術的なメカニズムについては、深い理解が共有できていたけれど、それ(組織的な戦術プレー)にこだわり過ぎて、局面での、「個」の創造的なボールコントロールを磨く作業が疎(おろそ)かになったという反省が為されたというわけさ。
そして、技術がしっかりとすれば、攻守にわたる様々な戦術イメージも、より効果的に、正確に、創造的に、機能させられる。
そして、攻守にわたって、「組織」と「個」がハイレベルにバランスするようなサッカーが、どんどんと進化・深化しつづける。
とはいっても・・
やっぱり難しいネ、「強さの本質」を、言葉で表現するのは・・。
まあ、とにかく、その視点で、ウルグアイは、ロシアに一日以上の長があった・・っちゅうことだね。
あっと・・
グループ「A」の、もう一つの最終戦では、アジアの仲間であるサウジアラビアが、北アフリカのエジプトに競り勝ったとのこと。
よかった・・
あっと・・まだ次のゲームまで2時間あるから、いまからリプレイを観ることにしよう。
そしてその後、グループ「B」の最終戦を楽しむっちゅうわけさ。
対戦カードは・・
トップのスペイン(勝ち点4)が、ボトムのモロッコ(勝ち点0)と、二位のポルトガル(勝ち点4)が、三位のイラン(勝ち点3)と対戦する。
私は、もちろん、同じアジアのイランの試合を観ますよ。
では、また〜〜・・
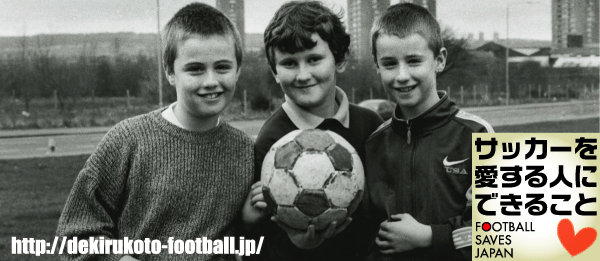 ”Football saves Japan”の宣言に賛同します(写真は、宇都宮徹壱さんの作品です)。
”Football saves Japan”の宣言に賛同します(写真は、宇都宮徹壱さんの作品です)。