湯浅健二の「J」ワンポイント
 2019年Jリーグの各ラウンドレビュー
2019年Jリーグの各ラウンドレビュー
 第7節(2019年4月13日、土曜日)
第7節(2019年4月13日、土曜日)
 スーパーレベルの攻撃サッカーマッチだった・・BSでの中継もあったんでしょ・・そりゃ、これ以上ない「J」のプロモーションになったはず・・バンザ〜イッ!・・そして両チームに感謝!!・・(マリノスvsグランパス、1-1)
スーパーレベルの攻撃サッカーマッチだった・・BSでの中継もあったんでしょ・・そりゃ、これ以上ない「J」のプロモーションになったはず・・バンザ〜イッ!・・そして両チームに感謝!!・・(マリノスvsグランパス、1-1)
 レビュー
レビュー
-
- 歴史に残る(それに値する!?)スーパーエキサイティングマッチだった。
ということで、今日は、どうして「そう」感じたのか・・っちゅうのがメインテーマですかね。
では、まず、こんな視点から・・
ゲームに没頭するなかで、「いつか、どちらかに決勝ゴールが入る・・」という確信を持てていた(手に汗にぎっていた!!)っちゅう、究極の緊張感。
実際・・
皆さんも観られたとおり、両チームともに、誰もが、「あっ、ゴールだっ!」ってフリーズするようなシーンを、最後の最後まで、繰り返し創り出しつづけたよね。
まあ、どちらのチームの「ゴール機会の量と質が上だったか・・」っちゅう議論は、ビデオを見返してみなきゃ、明確には判断できないよね。
あっと・・
会見冒頭のゲームインプレッションで、グランパス風間八宏監督が、一言だけ、「決めて欲しかった・・」って言っていたっけ。
確かにグランパス「も」、とてもエキサイティングなゴール機会を創り出しつづけた。
とはいっても・・サ・・
まあ、彼にしても、ビデオで、両チームが創り出した「ゴール機会」の内実をジックリと見直したら、「あ〜・・入れられなくてよかった・・」っちゅう安堵の感覚も、湧いてくるに違いないと思いますよ。
たぶんネ・・へへっ・・
とにかく・・
それほど両チームは、ものすごい勢いで、スペースを攻略し合ったんだ。
もちろんそれは、「ノーガードの打ち合い・・」などといった低次元の仕掛け合いじゃないよ。
そうではなく・・
あくまでも、両チームともに、全力の攻守ハードワークをブチかまし合ったということサ。
そう、両チームの強者どもは、例外なく、全力で、基本ポジションに縛られ過ぎることなく(!)攻守にわたる仕事(ハードワーク)を探しつづけたんだ。
もちろんそれは、「幾何学ロジック」を振りまわして悦に入っている、どこかの誰かさんレベルのハナシじゃないよ。
そう、だからこそこのゲームは、両チームにとって(!)、限りなく、「理想的な、ポジションなしのサッカー」へ向かっていたって言えると思うわけさ。
そこでの、典型的な(そしてスマートな!)ハードワークとは・・
それは、何といっても、相手ボールホルダーが、「後ろからの足音」を感じられないほど忠実&クレバーな「チェイス&チェック」と「ボール奪取」だったというわけさ。
そんなだから、両チームともに、仕掛けプロセスの途中でボールを失うシーンが続出するのも道理。
そして、これまた両チームともに、切れ味鋭い必殺カウンターをブチかます・・
だからこそ・・
観ている方にとっても、楽しく、ワクワクするサッカー(マリノス監督ポステコグルーの表現だよ!)になったっちゅうことだね。
______
あと二つだけ、簡単なテーマを・・
グランパスには、ジョーとかガブリエル・シャビエルとか、中盤の王様シミッチとか、優れた「天賦の才」に恵まれたスターがいる。
それに対して、「個人勝負プレー」では、グランパスほど押しの強くないマリノスは、究極の組織サッカーで対抗する。
だから、グランパスの最終勝負プロセスでは、どちらかといったら、ドリブル勝負や高さといった「個の武器の方が」目立っていたと思うんだよ。
それに対してマリノスは、あくまでも「組織」で最終勝負を仕掛けていく。
ここで言っているのは、あくまでも「傾向」のことだよ。
組織プレーといっても、そこに多くの「個人プレー」が内包されているのは、言うまでもないでしょ。
だから、あくまでも全体的な「選手たちの勝負イメージ」の傾向っちゅうこと。
ということで・・
そんな、少し「差異」のある、両チームの仕掛けの傾向にも目を凝らしていた筆者だったのです。
そして、両チームともに、自分たちの「強み」を、余すところなく前面に押し出せていたんだ。
そりゃ、感銘を受けない方が、おかしいでしょ。
そして、だからこそゲームが、極限のエンターテイメントっちゅう領域にまで成長していったっちゅうわけさ。
そして最後のテーマが・・
そんなマリノスの究極の組織サッカー。
それに関する私の質問に、ポステコグルーさんが、例によって真摯に、こんなニュアンスの内容をコメントしてくれたっけ。
・・わたしは、常に攻撃サッカーを志向している・・
・・そのマインドは、コーチ業をはじめてから今まで、変わることは全くなかった・・
・・もちろん、持ち駒(選手)のチカラの内実を前提に、もっとも実効レベルが高くなるようなタイプの組織サッカーを目指してはいるけれどネ・・
・・それが、このところの良いサッカーにつながっているのは嬉しい限りだ・・
・・たぶんそれは、観ている観客の皆さんにとっても、楽しいモノだと思う・・
そう・・
そのことは、観ている方たちだけじゃなく、やっている選手たちにとっても、まったく同じ。
マリノス選手たちが、悦びをもってプレーしているのが、ビンビンと伝わってくるじゃありませんか。
これで私は、マリノスを、3試合つづけて観戦したことになるのだけれど・・
彼らのサッカーが、さまざまな意味合いで、次元の高い「組織サッカー」へと進化&深化していることを体感できるのは、この上ない悦びじゃありませんか。
わたしは、そんなポステコグルー・マリノスが、好きだね。
あっと・・
もちろん私は、グランパスの風間八宏も、心からサポートしていますよ。
だから彼のチームが、「組織と個の特長」を高次元でバランスさせたサッカーで、結果も残していることに、心躍る思いなんだよ。
でも・・
そう、やっぱり、そこそこの才能レベルの選手たちを、一つのユニットとして、究極の組織サッカーへと導いているポステコグルー・マリノスに対する思い入れの方が・・!?
何といったって、オレは、現役時代は「汗かきミッドフィールダー」だったからサ・・
へへっ・・
============
最後に「告知」です。
どうなるか分からないけれど、まだ、連載をつづけています。
一つは、選択したテーマを深める「The Core Column」。
- そして、もう一つが、私の自伝、「My Biography」。
自伝では、とりあえず、ドイツ留学から読売サッカークラブ時代までを書きましょうかね。そして、もしうまく行きそうだったら、「一旦サッカーから離れて立ち上げた新ビジネス」や「サッカーに戻ってきた経緯」など、どんどんつづけましょう。
ホント、どうなるか分からない。でも、まあ、できる限りアップする予定です。とにかく、自分の学習機会(人生メモ)としても、価値あるモノにできれば・・と思っている次第。
もちろん、トピックスのトップページに「タイトル」をレイアウトしましたので、そちらからも入っていけます。
- まあ、とにかく、請う、ご期待・・ってか〜〜・・あははっ・・
-
===============
重ねて、東北地方太平洋沖地震によって亡くなられた方々のご冥福を祈ると同時に、被災された方々に、心からのお見舞いを申し上げます。 この件については「このコラム」も参照して下さい。
追伸:わたしは-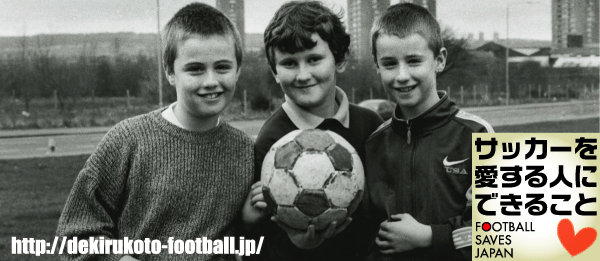 "Football saves Japan"の宣言に賛同します(写真は、宇都宮徹壱さんの作品です)。
"Football saves Japan"の宣言に賛同します(写真は、宇都宮徹壱さんの作品です)。
==============
ところで、湯浅健二の新刊。三年ぶりに上梓した自信作です。いままで書いた戦術本の集大成ってな位置づけですかね。
タイトルは『サッ カー戦術の仕組み』。出版は池田書店。この新刊については「こちら」をご参照ください。また、スポーツジャーナリストの二宮清純さんが、2010年5月26日付け日経新聞の夕刊 で、とても素敵な書評を載せてくれました。それは「こちら」です。また、日経の「五月の書評ランキング」でも第二位にランクされました。
-
-
-
-
 第7節(2019年4月13日、土曜日)
第7節(2019年4月13日、土曜日) スーパーレベルの攻撃サッカーマッチだった・・BSでの中継もあったんでしょ・・そりゃ、これ以上ない「J」のプロモーションになったはず・・バンザ〜イッ!・・そして両チームに感謝!!・・(マリノスvsグランパス、1-1)
スーパーレベルの攻撃サッカーマッチだった・・BSでの中継もあったんでしょ・・そりゃ、これ以上ない「J」のプロモーションになったはず・・バンザ〜イッ!・・そして両チームに感謝!!・・(マリノスvsグランパス、1-1)
 レビュー
レビュー
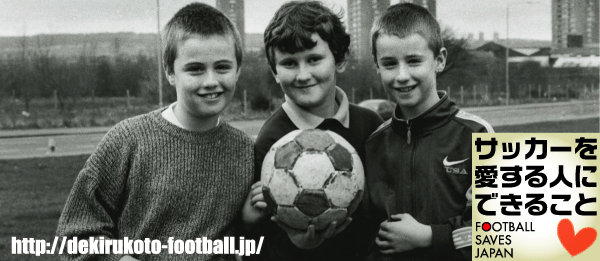 "Football saves Japan"の宣言に賛同します(写真は、宇都宮徹壱さんの作品です)。
"Football saves Japan"の宣言に賛同します(写真は、宇都宮徹壱さんの作品です)。