そのとき、本当にビックリし、そんな頓狂な声まで出してしまった。
何せ、普段は、眉根にしわ寄せるシリアスな表情で仕事をしているマネージャーの女性が、学内の上級マネージャーをメンザ(学生食堂)まで追いかけ、そして学生たちが見ている前で、その上級マネージャーのネクタイを、ハサミで「チョキン」と切り落としてしまったんだから。
私は、まさにフリーズ。
・・いったい、何が起きているんだろう・・これから大立ち回りが展開されちゃうんだろうか・・
そんな驚愕ハプニングを観ながら、「オレが知る由もない、ドイツの根深いネガティブ文化が暴発してしまう?」なんてコトまで考えていた。
とにかく、ほんの一瞬だけれど、フィジカル暴力の応酬とか、そんなネガティブなシーンまでも脳裏に浮かんだのだ。でも実際は・・
そう、周りの学生連中は、その驚愕シーンを、大笑いしながらはやし立てているんだよ。
・・いったい何が起きているんだ?・・
そのときの私は、外国人学生が大学に入学するためのドイツ語テストに合格したばかり。会話だって、おぼつかない。
だから、彼らが「はやし立てている」内容なんて分かるはずがないし、そこには、コトの背景を冷静に質問できるような友人もいなかった。
ビビりまくる私。それに対して、腹をかかえる学生たち。
フム〜〜ッ・・
■実は、ケルンのカーニバルがスタートしたんだ・・
ドイツ語では、「カルネヴァル」と発音するのが原語に近い。もともとはカトリックのお祭りだ。
カーニバルと言えば、ブラジルのリオや、イタリアのヴェネツィアを思い出す方が多いだろうけれど、ドイツでも、特にカトリック色の強い西部と南部で盛んなのだ。
なかでも、ライン川沿いのケルン、デュッセルドルフ、マインツなどが超有名だ。そう、わたしが住んでいたケルンは、ドイツ・カーニバルのシンボル的な都市だったんだよ。
でも私は、そのことについて、ウリも含めて、学生仲間やサッカークラブのチームメイトの誰からも教えられていなかった。
もちろん彼らは、カーニバルを心待ちにしていた。にも関わらず、私との会話には、その話題など出てきた例(ため)しがなかったんだ。
いや、彼らのなかでは話題になっていたけれど、こちらが、その内容をうまく理解できていなかっただけなのかもしれない。
とにかく私は、お恥ずかしながら、カーニバルについて、そのときまで全く知らなかったんだよ。
あんなに楽しく盛り上がる、町を挙げての「無礼講パーティー」をだよ。
フ〜〜ッ・・
「どうして教えてくれなかったんだよ・・!」
ウリに対して、文句を言った。そしたら・・
「えっ!? オマエ、知らなかったのか? 信じられない。ケルンにくる外国人は、誰もが、一番それを楽しみにしていると思っていたのに・・」などと、シラッとして言うんだよ。
ウリに質問できたのは、メンザ(学生食堂)での「ネクタイ・チョキン事件」があった直後。ウリの授業が終わってヤツがメンザに現れたタイミングだった。
■それは、女のカーニバル(Weiberfastnacht)から全てが始まる・・
その「ネクタイ・チョキン事件」があったのは、木曜日の午後のことだった。
その日が、まさにカーニバルの初日だったというわけだ。それは、女性が、社会の主導権を握ってもよいとされている日なのだ。
場所によっては、女性たちが市庁舎に「なだれ込む」なんていうイヴェントがおこなわれる町もあると聞く。
だから、男性のネクタイを「チョキンッ!」しても、誰も文句を言えないっちゅうわけだ。
ちなみに、その日に限って男性は、自分が気に入っているネクタイを着けないというのが不文律ということだった。
あっと・・、女のカーニバルからはじまるケルンの「カルネヴァル」。
その「女の木曜日」から、学校や官庁も「開店休業状態」になってしまうなど、「あの」厳格なドイツ社会が、完璧に「ファジー」に変身しちゃうんだ。もちろん私は、面食らっていた。
そしてカーニバルは、その日の夕方から、次の週の水曜日(Aschenmittwoch=灰の水曜日と呼ばれる!)まで、町をあげた「無礼講パーティー」に盛り上がりつづけるっちゅうわけだ。
うまく表現できないけれど、とにかく、カーニバル期間中のドイツ人は、完璧に人が変わる・・と感じていた。
いや、本当は、常に型にはまった「厳格」さがコンセプトであるドイツ社会だからこそ、そのときだけは、タガを外して、とことん(自分自身を!)解放しちゃおう・・っちゅう「意志」が社会全体にあふれかえる・・なんていう表現の方が的を射ているかもしれない。
そう・・、「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら、踊らにゃソンソン・・」っちゅうわけだ。
そういえばドイツ人は、長く、暗〜い「冬」を乗り切るために(!?)、学校や会社、各種クラブや地域社会、はたまたファミリーや個人による、自分たち主体のパーティーを企画し、それをとことん楽しむというメンタリティーをもっているんだっけ。
そんな「楽しみ」が、日常の(四角四面の!?)社会生活を、真面目に、そして高効率に「こなして」いくための大いなるモティベーションになっているのかもしれない。
そして、そんな「日常の小さな楽しみ」の集大成が、カルナヴァルっちゅうことなのかもしれない。
そしてドイツ人は、そのイヴェントをとことん楽しみ尽くそうと、ドイツ的な真面目さで(!?)全力を傾注するっちゅうわけだ。
とにかく、「あの」ドイツ人が・・だからね、その「徹底さ」は、推して知るべしなのだよ。
フムフム・・へへっ・・
■まずウリと、ケルンのドーム(大聖堂)近くにある「アルトシュタット」へ行ってみた・・
アルトシュタット・・
それは、ドイツの伝統的な古い町並みが残る歓楽街のことだ。
まあ、そこは、社会人の歓楽街といってもいいかな。
要は、少し「値の張る」中級以上の飲食店が多いということだ。だから、学生だった我々は、めったにアルトシュタットへ繰り出すことはなかった。
でも、そのときはカーニバルだからね、色々なウワサで、そこが、特に初日の木曜日の夜、もっとも盛り上がるということだった。出掛けていかない手はないじゃないか。
実は、ウリも、カーニバルについては、「新人」に近かったんだよ。
何せヤツは、(当時の)東ドイツから逃げてきた「逃亡者」で、そのときは、(憧れだった!?)アメリカ旅行から帰ってきたばかりだったからね。
その経緯については、この連載で発表した「ウリの逃避行シリーズ」をご参照アレ。
あっと・・アルトシュタット。
ということで我々は、ライン川沿いの、ちょっと「ハイソ」な歓楽街のセンター広場に立った。
フムフム・・、たしかに盛り上がっているじゃないか。中央にはステージが設けられて、様々なショーが真っ盛りだ。
そこは、アルトシュタット(ハイソ歓楽街)に隣接する「ホイマルクト」と呼ばれる広場。
ケルンにも、いたるところに「マルクト」と呼ばれる市場(空き地=広場)が点在している。
そのホイマルクトは、ケルン中心街にある、もっとも有名なノイマルクト(英語=ニューマーケットスクウェア)と並び、ケルンを代表する「マルクト広場」なのだ。
普段のウイークエンドや休日は、生鮮野菜や食べ物などの屋台市場やフリーマーケット会場などとして機能する「マルクト広場」だけれど、カーニバルのときは、もちろん最高の「イヴェント広場」として活用される。
そんな「ホイマルクト」で催された、カーニバルのオープニングセレモニーだからネ、そりゃ、盛大になるのも当たり前だ。
「オレさ・・実は、ケルンのカーニバルに、本当の意味で参加するのは今回がはじめてなんだ・・」
ウリが、そんなことを告白していた。その背景は、前述したとおりだ。彼にとってもケルン(西ドイツ)は、まだまだ「外国」だったというわけだ。
でも、「ホイマルクト」の雰囲気は、もう最高潮。その盛り上がり方は、サッカーのブンデスリーガマッチにも引けを取らないな・・なんて感じたモノだった。
そのとき・・
■女性も、「ドイツ的なお堅い雰囲気」から解放されている・・
「ネ〜・・ネ〜・・アナタは、アジア人よね・・どこから来たの?」
「えっ・・あ〜・・ヤーパン(日本)です・・」
「エッ!?・・日本人?・・へ〜っ・・わたし、日本のことは好きよ・・それにしてもアナタは背が高いわね〜・・日本人じゃないみたい・・だって彼らは、おしなべて背が低いじゃない?・・」
「そうですよね〜・・一般的に日本人は背が低いですよね〜・・でも私は、例外なんですよ・・日本の学校でも、いつも一番背が高かったんです・・」
「それにしても、アンタいい男だね〜・・ね〜ね〜・・これから、何か予定があるの?・・私たちに付き合いなさいよ・・」
その30代とおぼしき女性の二人組は、まったく臆することなく、そんな風に我々を誘ってきた。
飲み屋でも、そんなコトはあまり経験したことがなかった。
もちろん飲み屋でも、よく女性と知り合いになった。でも、眼が遭ったことをキッカケに、まず話し掛けるのは男の方から・・というのが普通の流れなのだ。
まして、そのときは、「ホイマルクト」という屋外の広場だし、飲み屋ほど、人の密度は高くないから、雰囲気は、とても「スペーシー」なモノだったんだよ。
そして、そこが、「解放された非日常の空間・・」という事実を再認識させられたというわけだ。
あっと・・。ということは、彼女たちは、もうかなりアルコールが入っていたっちゅうことなのか?
いや、それは思い過ごしだった。彼女たちは、まったく「しらふ」で、我々を誘ってきたのだよ。
彼女たちは我々よりも年上だけれど、見た目でも、話し方にしても、いわゆる「いい女」の部類に入る二人連れだった。だから、食指が伸びそうになるのも道理だった。でも・・
そう、そのとき我々は、招待されていた学生仲間のパーティーへ向かおうと広場を後にしようとしていたタイミングだったんだよ。
そのパーティーには女子学生も大勢くるから、まあ、そちらの方が優先順位は高い。
それにしても・・
その「いい女」の二人組は、普段は、こんな感じで男に声を掛けることなど皆無に違いない。ただ、そこはカーニバル。彼女たちも、完璧に「解放」されていたのだと思う。
そんなコトを書きながら、当時の私のなかで、「非日常」を経験しながら、カーニバルに対する「様々な期待」が、どんどんと盛り上がっていったことを思い出していた。
へへっ・・
結局われわれは、その二人組に別れを告げ、アルトシュタットで催された開幕アトラクションを後にすることにした。
ちょっと後ろ髪は引かれたけれど、でもそれ以上に、「あるコト」に束縛されたり集中したりするのではなく、とにかく大っぴらに解放されるなかで、とことんカーニバルを体感したいという欲望がふくらんでいたのである。
だから、とにかく色々なイベントに顔を出すことにしたんだ。
(つづく)
============
これまでの「My Biography」については、「こちら」を見てください。
===============
重ねて、東北地方太平洋沖地震によって亡くなられた方々のご冥福を祈ると同時に、被災された方々に、心からのお見舞いを申し上げます。 この件については「このコラム」も参照して下さい。
追伸:わたしは
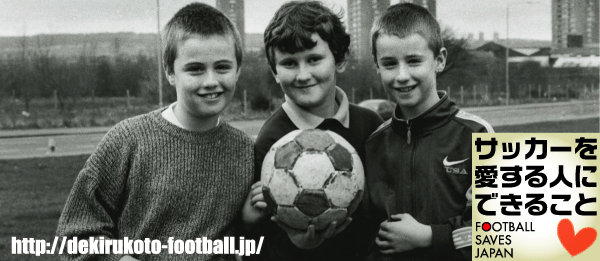 ”Football saves Japan”の宣言に賛同します(写真は、宇都宮徹壱さんの作品です)。
”Football saves Japan”の宣言に賛同します(写真は、宇都宮徹壱さんの作品です)。
==============
ところで、湯浅健二の新刊。三年ぶりに上梓した自信作です。いままで書いた戦術本の集大成ってな位置づけですかね。
タイトルは『サッ カー戦術の仕組み』。出版は池田書店。この新刊については「こちら」をご参照ください。また、スポーツジャーナリストの二宮清純さんが、2010年5月26日付け日経新聞の夕刊 で、とても素敵な書評を載せてくれました。それは「こちら」です。また、日経の「五月の書評ランキング」でも第二位にランクされました。